はじめに
もう先月のことになりますが、知人というか友人というか元同僚と「芸術」について論争(?)する機会がありました。その際、芸術に対する自分なりの意見をPDFにまとめてLINEで彼に送りつけたのですが、その時の文章が現時点での自分の考えをよく表現できている気がするので、久々のブログ更新のネタとしてここで公開したいと思います。
事の発端は、坂口安吾の『文学のふるさと』という評論文が文学、ひいては芸術の本質を的確に捉えている!と、筆者(僕)が熱っぽく語ってしまったことにあります。
ただ熱く語るのなら問題ないのですが、筆者の悪い癖として何かを持ち上げるために他を貶めるという悪手を打ってしまったため(例:近代文学こそ至高であり現代の小説はクソ、漱石・芥川・太宰が本道であり谷崎・川端・三島は海外ウケだけ、等々)、何だか独りよがりな持論を押し付ける形になってしまいました。
後日、彼から反論&補足の長文LINEが送られてきました。
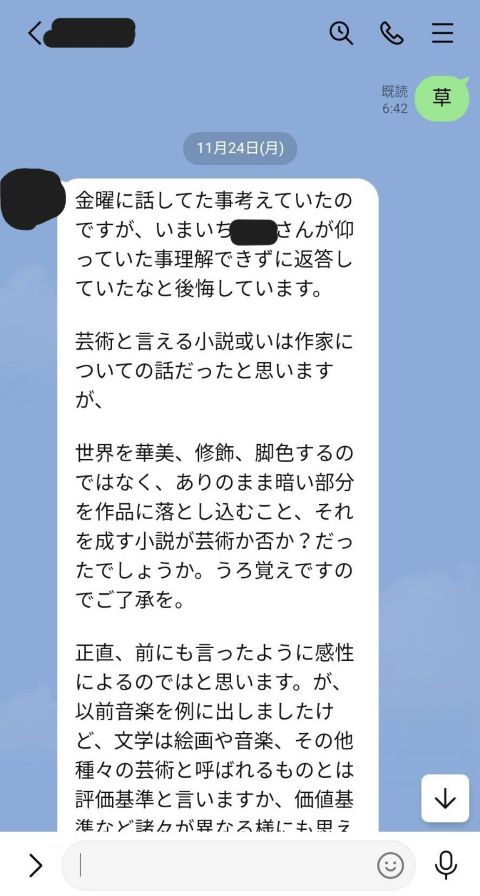
メッセージの内容を大まかに要約すると、以下のようになります。
世界を美化せず、現実の暗い部分を作品に反映するのが芸術だという話だったが、それは各々の感性による。話の筋の面白さ(エンタメ性)の正否も一概には言えない。
芸術性のあるものは名前が残るという話があったが、大衆に芸術を判断することはできないため、大衆の間における知名度は作品の価値とは結び付かない。芸術は昔からの積み重ねで成り立っており、その分野の人間にしか判断できない。
幼児が描いた絵や、壁に物体を貼り付けただけの作品は芸術ではない。金持ちが値を付けることで芸術が歪められてしまう。(現代アート批判?)
負けじとさらに長文のLINEを送り返すために、これらの内容を踏まえた上で自分なりに「芸術」の定義について考えてみたのですが、考えながら書いているうちに思いの外筆が乗ったため、PDFファイルにまとめて送ることになりました。
以下に載せるのがその時送った文章です。改めて読み返すとアレな部分もありますが、わざわざ修正するのも大儀なので、そのまま載せようと思います。文末の「ですます」調が途中で変わったり、後半引用だらけになったりしますが、その辺は勢いのまま書いたためご了承ください。後半の引用は持論を長々と説明するよりも、その持論に当てはまる作家の文章を直接読んでもらった方が言わんとしていることが伝わると思ったからです。決して書くのが面倒くさくなったわけではありません。。。
芸術とは何か
この命題に関しては、今日に至るまで哲学者や作家を含む様々な人間がそれぞれ独自の意見を持ち、論じてきながらも、今なお結論に至っていないようです。したがって、僕という一人の人間ごときがここでその本質を完璧に述べることは不可能だと思います。
あるいは、生命やSF、お好み焼きの定義が人それぞれで議論を呼ぶように(関西人の僕にとって広島焼きはお好み焼きとは別の何かです)、芸術も一人ひとりの中で自分なりの自由な定義が存在しても構わないのかもしれません。むしろ、時代を変えてしまうような芸術作品が登場する時、その作品がそれまでの芸術作品を破壊あるいは否定してしまうような強烈な新奇性を持っていることは往々にしてあるので、「これが芸術である」という概念の固定化自体が芸術の本質から遠ざかっているような気もします。(先代を学びながらもこれを疑い、乗り越えていくというのは哲学と共通の姿勢ではないでしょうか。)実際、印象派の絵は当時のサロンの画家からすれば考えられない代物だったでしょうし、漱石や鴎外は自然主義が主流の当時の日本文壇では「異端」でした。
一方で、どの芸術作品においても変わらない原則があります。それは、人間が何かを表現しようとする行為がその起点であることです。では、この原則さえ満たしていれば、そこから生まれた作品は芸術と呼ぶに値するのでしょうか?
僕はここでは大胆に、然り、と答えたいと思います。芸術とは、あらゆる人間の表現行為である―――これが、現時点の僕が考える広い意味での『芸術』です。
したがって、幼児が自分の両親をクレヨンで表現しようとするのも、既存の芸術へのアンチテーゼを目的として壁にバナナを貼り付けるのも芸術の一種であると僕は考えます。
もちろん、ある人間が表現したものに対して、その技術の巧拙の評価や鑑賞者の数の多寡は違ってくるでしょう。しかし、表現されたものがその後どのような経緯を辿るかということが芸術か否かを決定的に左右する要因になるとは思えません。というのも、作品の評価などは時代によって移り変わるものですし、同じ作品についてどのような評価を下すのかということも結局のと ころ鑑賞者個人の好みに左右されるからです。
浮世絵は当時の日本国内においては単なる通俗文化の一種と見なされていたそうですが、後の西洋の画家たちにとっては立派な芸術でした。また、開国後の日本の文学の歴史を眺めても、その時代において大衆的な人気や評価を獲得していながらも、後の時代には全く顧みられていない小説というものは少なくないようです。このように、ある作品の評価は時代によって変わり得るものであり、したがって、現時点での評価を使って芸術か否かを判断するのは不十分であると考えられます。また、現在忘れ去られている作品の内の一つが将来、再評価されるという可能性もないとは言えません。例えば、ダンテの「神曲」やフィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」のような今日では傑作と評価されている作品ですら、全く忘れ去られていた時代や絶版になっていた時代があったそうです。(そして、これらの作品がまた忘却の彼方に追いやられるという可能性もやはり無いとは断言できないのです。)
僕は今まで、その作家の名前や作品が残ったものが真の芸術だという風に考えていましたが、上に述べたような事情を考えると短絡的な結論であったと感じます。(ちなみにここで言う「名前が残る」というのは、「一定の感性をもった人々の間で、ささやかにでもその作品が読み継がれていく」という意味です。僕は大衆の間に名前が残っているかどうかなど全く重視していません。少しでも文学に関心がある人間ならばフランツ・カフカという作家を知っていることは「当然」ですが、大衆の中には皆無でしょう。)教科書というのは、アカデミズムの世界において名前が残っている作家を知るのに手っ取り早い手段ですが、教科書の内容というものがいつでも変わり得るという事実を考えると、やはりそこに載っている作家のみを芸術として認めるというのは普遍的な基準ではないでしょう。
さらに、同時代においても各個人によって作品の評価というのは変わってきます。僕は高校の頃、授業で太宰治の「富嶽百景」を読んだ際に、普段文学とは無縁そうな派手目の女子(と言っても、受験をパスしているので偏差値はそれなりにあるのですが)が「結構面白かった」という感想を友人に話しているのを聞いて密かに喜びを感じた経験があります。しかし、そのように感じたのはその子くらいで、やはり大半のクラスメイトはこの作品の良さを僕が感じるのと同じようには感じなかっただろうと思います。一方で、僕も世間でヒットしているような映画や若者向けの恋愛映画に全く心を動かされないということはよくあります。これも、「感性の差」というものなのでしょう。
僕としては多少なりとも文学に親しんできた自分の感性の方を信用したいのですが、感動というのが主観的な体験である以上、彼らの感動と僕の感動の優劣をここでつけることは不可能なことのように思われます。僕は今まで、文学を含む芸術分野にはいわゆる「分かる人」と「そうでない人」が存在し、自分がその「分かる人」の一人だと考える傾向にあったのですが、よくよく考えてみると何をもって「分かる」とするかなどは、恣意的なものだと言わざるを得ないと感じます。
「餅は餅屋」とは言いますが、では文学に精通し、理解している人間というのはどういう種類の人間なのでしょうか?大学の文学部の教授は文学を理解し、正当に評価できるものでしょうか?もしそうであり、そこで研究されている作品や作家のみが文学ならば、それは単なる権威主義ではないでしょうか?先ほど述べた通り、教科書はいつでも変わり得るのです。
古典を大量に読み込んでいる読書家ならどうでしょうか? 確かに彼らはそれらの古典のエッセンスを感じ取り、それを知識として自分の中にため込むでしょう。では、そのような人々はその知識を用いて、現在生まれつつある「新たな才能」を発見できるのでしょうか?彼らは既に評価が確立した古典については共通の見解を持つこともできますが、現在新たに出版され続けている作品についてはそれぞれ意見を異にするでしょう。そこにはやはり、個人の好みの問題が入り込むため、誰が本当に「分かっている」のかを決定づける基準などない気がします。
また、知識偏重の姿勢は芸術の持つ主観的な側面を無視してしまう危険性をはらんでいます。例えば、これは代表的な日本の現代美術家である村上隆の発言だったと記憶しているのですが、現代アートを鑑賞するためには西洋美術史の文脈を学んでいることが必須であるそうです。印象派の登場やセザンヌによる多視点の導入、キュビズム、ダダイズム、さらに抽象絵画へ……。このような流れの中において、デュシャンの「泉」や、壁に貼り付けられたバナナのようなコンセプチュアル・アートが初めて鑑賞できるとのことです。ピカソの絵も同様でしょう。
では、そのような文脈を詳しく知らない人間(僕も含め)が絵画に感動しないのかというと、そんなことはありません。僕らは SNS に流れてくるイラストに心を動かされることがありますし、新海誠映画の美麗な映像に感動することもあります。そして、これらの通俗文化も浮世絵のように後世に芸術として評価される可能性を持っているのです。また、このような西洋絵画の文脈の外に位置する芸術―――アステカ文明やマヤ文明といった古代メソアメリカの絵画など―――も、それによって感銘を与えないという訳ではないため、やはり芸術の一つでしょう。サロン絵画や宮廷音楽、和歌のように、一定の型や知識を前提として作られていく芸術というのは多く存在し、それらを「理解できる」ことが貴族の権力とも結びついていた訳ですが、新たな芸術が必ずその型の外部から登場してきた歴史を考えてみれば、それも絶対的な基準とは言えないでしょう。
このように「分かる」ことだけを芸術とするならば、芸術は「知」の権力に基づいた単なる謎解きゲームに変わってしまいます。分析的な解釈や客観的な論理性は芸術を批評する上で重要なものですが、やはり主観的な感動というものも芸術の要素の一つでしょう。そしてそれは知識に通じたある限られた人のみが感じられるというものでもないのです。先ほどの高校のクラスメイトの女子の例のように、大衆を含めたあらゆる人々に開かれている優れた芸術というのもあるように思われます。
また、アート作品に高額な値が付くというのはニュースでよくある話ですが、これは市場原理の話であって芸術の本質的な価値とは何の関係もない話だと思います。チューリップの球根から株券、ポケモンカードに至るまで自由市場ではあらゆるものは取引対象あるいは投機対象になり得ますし、芸術作品がその一つになるというのも、正しいかどうかは別にして特に疑問ではないです。ただし、その市場で付いた値段とその芸術作品の価値を混同するのは明らかに誤りであり、貨幣に毒された現代人の悪い癖だと思います。
ここまで長々と述べてきたことをまとめると、ある芸術作品の評価や需要のされ方というのは時代や個人によって変わり得る相対的なものなので、それをいくら眺めたところで芸術の絶対的な価値基準というものは発見できないということです。そうであるならば、芸術の定義はその終点ではなく起点に、―――誰かが何かを表現しようとする行為に求めるしかないでしょう。鑑賞者の存在はここでは棄却してしまっても構わないと僕は思います。
あるいは、鑑賞者の中には作品を作った「その人自身」も含まれると考えればどうでしょうか?精神医学の心理療法の中にはコラージュ療法や創作療法、箱庭療法のような、作品を制作することで心の安定を図る治療が存在します。ここで重要なのは患者が作品によって自己を表現し、それを改めて鑑賞することで自己を理解することです。鑑賞者は自分自身であり、他者の存在は基本的に考えません。しかし、そこで作った作品が自分自身に何かを与え、物事を理解するための助けになるならば、それはある作家の作品を読んで人生に影響を受ける体験と大きな差はないでしょう。
表現行為が芸術であるならば、あとはその芸術の結果が好まれるか否かというだけです。好む人がある程度いれば評価されますし、いなければそれっきりです。時の洗練に耐え、その作品が後の時代にも残っていくかは結果論でしかありません。もしカフカの作品が彼が亡くなった時点で散逸してしまい、今日まで残ることがなく、誰も彼の名前を覚えていなかったとしても、やはりそこに芸術はあったのです。同様に、僕らの知らない芸術というものが古今東西あらゆる場所において存在したでしょうし、あるいは存在するのでしょう。短命に終わった詩人や芸術家の生涯、戦火によって失われた作品を見れば、そのような可能性を考えない訳にはいかないのです。
したがって、僕がこれから述べるのは僕個人がどのような芸術を好み、評価するかという『僕にとっての芸術論』に過ぎません。他の人と考えが違っても一向に構いませんし、その固有性こそが芸術の本質の一つではないかと思っています。そういう意味では、芸術とは孤独なものです。
しかし、誰が孤独でない人がいるでしょうか?どんな人間も、現在・過去・未来に存在する自分以外の人間と全く同じ生き方をすることはあり得ませんし、全く同じ生き方をしない以上、何に心を動かされ、何を表現しようとするかはそれぞれ違っていて当然なのです。
そのような世界で自分の価値観や世界観(すなわち、その人にとっての『芸術』)と近い考えを持った人間に出会うというのは滅多にないことですし、幸運にもそのような機会に巡り合えた時、初めて真の共感や感動というものが訪れるのだろうと思います。生憎、僕は生身の人間で自分と同じように世界を捉えていると感じる人間に出会ったことはまだありませんが、かつて生きていた人間の中になら、幾人かいます。そしてそれは、他でもなく彼らの残した作品を鑑賞し、それによって深く心を動かされたということです。
結局のところ、僕がある芸術作品を愛好し、時にはその作者ごと関心を持つというのは、自分と気の合う友達とのおしゃべりに夢中になるというような一般的な喜びとそれほど変わりはないことなのかもしれません。
(改めて)芸術とは何か
僕の好む芸術―――理想主義と現実主義の間の葛藤、リヒリズムの中でなおロマンを見出そうとする努力、エゴイズムの自覚を持ちながらも愛を追及する勇気。それらの闘いの結果は問わない。仮に敗北したとしても構わない。むしろ、勝つことは不可能だというのが不条理な人生の結論かもしれない。それでも戦うこと。
意味の幻想の中に生きるのは幸福なことだろう。宗教、政治的イデオロギー、学歴競争、出世競争、恋愛、婚活、ナショナリズム、戦争。ここでは愛は情熱的であり、成功は輝かしく、死さえ英雄的である。しかしこれらの幻想が何かの拍子にはがれ落ち、物質的な世界に直面したときあらゆる物事は単なる物理現象に還元されてしまう。愛も、死も、意識も……。そこには、何の意味付けもされていない不条理な運命があるだけである。あらゆる歴史的事象とそこで生き、死んで来た人々は、現在の世界にもあり、また将来にも繰り返されるだろうと感じる。そして、何の意味もなく永遠に回り続けるこの世界で、人類の愚かさの中で生き続ける苦しみだけが残る。
しかし、一度地下には潜らなければならない。光差す明るい地上のもとで、草木や鳥に囲まれながら「世界は美しい!」と唄うことに何の説得力があるのか。死んでいった人々の骨、地上から排除された捨て猫たち、滅んだ文明の残骸……、それらに満たされた寒々とした地下世界を芸術家は眺める。そこではあらゆる意味ははく奪されている。しかし、その暗闇の中で何とか一筋の光明を見つけようとする。運よく地上に戻れた時、彼は唄い出す―――「世界は美しい!」
言葉は同じでも意味は全く違う。僕らは強制収容所に送られたヴィクトール・フランクルが「"それでも"人生にイエスという」と言った意味をもう一度考えなければならない。
―――以下、僕が思う芸術家たち。
夏目漱石
呑気と見える人々も、心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音がする。
引用:『吾輩は猫である』
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ。情に棹せば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
(中略)
越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容げて、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降くだる。あらゆる芸術の士は人の世を長閑(のどか)にし、人の心を豊かにするが故に尊い。
引用:『草枕』
世に住むこと二十年にして、住むに甲斐ある世と知った。二十五年にして明暗は表裏のごとく、日のあたる所にはきっと影がさすと悟った。三十の今日はこう思うている。――喜びの深きとき憂いいよいよ深く、楽みの大いなるほど苦しみも大きい。これを切り放そうとすると身が持てぬ。片づけようとすれば世が立たぬ。金は大事だ、大事なものが殖えれば寝る間も心配だろう。恋はうれしい、嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔がかえって恋しかろ。閣僚の肩は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまい物も食わねば惜しい。少し食えば飽き足らぬ。存分食えばあとが不愉快だ。……
引用:『草枕』
We look before and after
And pine for what is not
Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
(筆者注:パーシー・ビッシュ・シェリーの詩の引用、以下拙訳
“前を見ては後ろを見ては、ここにないものに恋焦がれる
心の底からの笑いには、いくらかの苦悩が満ちている
最も甘美な歌たちは、最も悲しい想いを伝える歌だ”)
引用:『草枕』
(筆者注:主人公の三四郎は大学の先輩の家に泊まった夜、近所で鉄道自殺に遭遇する)
三四郎は無言で灯の下を見た。下には死骸が半分ある。汽車は右の肩から乳の下を腰の上まで美事に引きちぎって、斜掛の胴を置き去りにして行ったのである。顔は無創である。若い女だ。
(中略)
三四郎の目の前には、ありありと先刻の女の顔が見える。その顔と「ああああ……」と云った力のない声と、その二つの奥に潜んでおるべきはずの無残な運命とを、継合わして考えてみると、人生という丈夫そうな命の根が、知らぬ間に、ゆるんで、何時でも暗闇へ浮き出して行きそうに思われる。三四郎は慾も得もいらない程怖かった。ただ轟と云う一瞬間である。その前までは慥(たし)かに生きていたに違いない。
引用:『三四郎』
「私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用できないから、人も信用できないようになっているのです。自分を呪うより外に仕方がないのです」
「そうむずかしく考えれば、誰だって確かなものはないでしょう」
「いや考えたんじゃない。やったんです。やった後で驚いたんです。そうして非常に怖くなったんです」
(中略)
「とにかくあまり私を信用してはいけませんよ。今に後悔するから。そうして自分が欺むかれた返報に、残酷な復讐をするようになるものだから」
「そりゃどういう意味ですか」
「かつてはその人の膝の前に跪いたという記憶が、今度はその人の頭の上に足を載せさせようとするのです。私は未来の侮辱を受けないために、今の尊敬を斥けたいと思うのです。私は今より一層淋しい未来の私を我慢する代りに、淋しい今の私を我慢したいのです。自由と独立と己とに充ちた現代に生れた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないでしょう」
引用:『こころ』
芥川龍之介
幻滅した芸術家
ある一群の芸術家は幻滅の世界に住している。彼らは愛を信じない。良心なるものをも信じない。唯昔の苦行者のように無何有の砂漠を家としている。その点は成程気の毒かもしれない。しかし美しい蜃気楼は砂漠の天にのみ生ずるものである。百般の人事に幻滅した彼らも大抵芸術には幻滅していない。いや、芸術と云いさえすれば、常人の知らない金色の夢は忽ち空中に出現するのである。彼等も実は思いの外、幸福な瞬間を持たぬ訣(わけ)ではない。
引用:『侏儒の言葉』
庸才
庸才の作品は大作にもせよ、必ず窓のない部屋に似ている。人生の展望は少しも利かない。
引用:『侏儒の言葉』
「僕か? 僕は超人(直訳すれば超河童です。)だ。」
トックは昂然と言い放ちました。こう云うトックは芸術の上にも独特な考えを持っています。トックの信ずる所によれば、芸術は何ものの支配をも受けない、芸術の為の芸術である、従って芸術家たるものは何よりも先に善悪を絶した超人でなければならぬと云うのです。
(中略)
僕は或月の好い晩、詩人のトックと肘を組んだまま、超人倶楽部から帰って来ました。
トックはいつになく沈みこんで一ことも口を利かずにいました。そのうちに僕等は火かげのさした、小さい窓の前を通りかかりました。その又窓の向うには夫婦らしい雌雄の河童が二匹、三匹の子供の河童と一しょに晩餐のテエブルに向っているのです。するとトックはため息をしながら、突然こう僕に話しかけました。
「僕は超人的恋愛家だと思っているがね、ああ云う家庭の容子を見ると、やはり羨しさを感じるんだよ。」
「しかしそれはどう考えても、矛盾しているとは思わないかね?」
けれどもトックは月明りの下にじっと腕を組んだまま、あの小さい窓の向うを、――平和な五匹の河童たちの晩餐のテエブルを見守っていました。それから暫くしてこう答えました。
「あすこにある玉子焼は何と言っても、恋愛などよりも衛生的だからね。」
引用:『河童』
一 時代
それは或本屋の二階だつた。二十歳の彼は書棚にかけた西洋風の梯子に登り、新らしい本を探していた。モオパスサン、ボオドレエル、ストリントベリイ、イブセン、シヨウ、トルストイ、……
そのうちに日の暮は迫り出した。しかし彼は熱心に本の背文字を読みつづけた。そこに並んでいるのは本というよりも寧ろ世紀末それ自身だつた。ニイチエ、ヴエルレエン、ゴンクウル兄弟、ダスタエフスキイ、ハウプトマン、フロオベエル、……
彼は薄暗がりと戦いながら、彼等の名前を数えて行った。が、本はおのずからもの憂い影の中に沈みはじめた。彼はとうとう根気も尽き、西洋風の梯子を下りようとした。すると傘のない電燈が一つ、丁度彼の頭の上に突然ぽかりと火をともした。彼は梯子の上に佇んだまま、本の間に動いている店員や客を見下ろした。彼等は妙に小さかった。のみならず如何にも見すぼらしかった。
「人生は一行のボオドレエルにも若かない。」
彼は暫く梯子の上からこう云う彼等を見渡していた。……
引用:『或阿呆の一生』
十九 人工の翼
(中略)
人生は二十九歳の彼にはもう少しも明るくはなかった。が、ヴオルテエルはこう云う彼に人工の翼を供給した。
彼はこの人工の翼をひろげ、易やすと空へ舞ひ上った。同時に又理智の光を浴びた人生の歓びや悲しみは彼の目の下へ沈んで行った。彼は見すぼらしい町々の上へ反語や微笑を落しながら、遮ぎるもののない空中をまっ直ぐに太陽へ登って行った。丁度こう云う人工の翼を太陽の光りに焼かれた為にとうとう海へ落ちて死んだ昔の希臘(ギリシヤ)人も忘れたように。……
引用:『或阿呆の一生』
或声 人生はそんなに暗いものではない。
僕 人生は「選ばれたる少数」を除けば、誰にも暗いのはわかっている。しかも又「選ばれたる少数」とは阿呆と悪人との異名なのだ。
引用:『闇中問答』
僕は二度も僕の目に浮かんだダンテの地獄を詛(のろ)いながら、じっと運転手の背中を眺めていた。そのうちに又あらゆるものの嘘であることを感じ出した。政治、実業、芸術、科学、――いずれも皆こう云う僕にはこの恐しい人生を隠した雑色のエナメルに外ならなかった。僕はだんだん息苦しさを感じ、タクシイの窓をあけ放ったりした。が、何か心臓をしめられる感じは去らなかった。
引用:『歯車』
僕は妻の実家へ行き、庭先の籐椅子に腰をおろした。
(中略)
「静かですね、ここへ来ると。」
「それはまだ東京よりもね。」
「ここでもうるさいことはあるのですか?」
「だってここも世の中ですもの。」
妻の母はこう言って笑っていた。実際この避暑地も亦「世の中」であるのに違いなかった。僕は僅かに一年ばかりの間にどのくらいここにも罪悪や悲劇の行われているかを知り悉していた。徐ろに患者を毒殺しようとした医者、養子夫婦の家に放火した老婆、妹の資産を奪おうとした弁護士、――それ等の人々の家を見ることは僕にはいつも人生の中に地獄を見ることに異らなかった。
引用:『歯車』
我々人間は人間獣である為に動物的に死を怖れている。所謂生活力と云うものは実は動物力の異名に過ぎない。僕も亦人間獣の一匹である。しかし食色にも倦いた所を見ると、次第に動物力を失っているであろう。僕の今住んでいるのは氷のように透み渡った、病的な神経の世界である。僕はゆうべ或売笑婦と一しょに彼女の賃金(!)の話をし、しみじみ「生きる為に生きている」我々人間の哀れさを感じた。若しみずから甘んじて永久の眠りにはいることが出来れば、我々自身の為に幸福でないまでも平和であるには違いない。しかし僕のいつ敢然と自殺出来るかは疑問である。唯自然はこう云う僕にはいつもよりも一層美しい。君は自然の美しいのを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑うであろう。けれども自然の美しいのは僕の末期の目に映るからである。僕は他人よりも見、愛し、且又理解した。それだけは苦しみを重ねた中にも多少僕には満足である。
引用:『或旧友へ送る手記』
宮沢賢治
三八四 告別
おまえのバスの三連音が
どんなぐあいに鳴っていたかを
おそらくおまえはわかっていまい
その純朴さ希みに充ちたたのしさは
ほとんどおれを草葉のように顫(ふる)わせた
もしもおまえがそれらの音の特性や
立派な無数の順列を
はっきり知って自由にいつでも使えるならば
おまえは辛くてそしてかがやく天の仕事もするだろう
泰西著名の楽人たちが
幼齢弦や鍵器をとって
すでに一家をなしたがように
おまえはそのころ
この国にある皮革の鼓器と
竹でつくった管とをとった
けれどもいまごろちょうどおまえの年ごろで
おまえの素質と力をもっているものは
町と村との一万人のなかになら
おそらく五人はあるだろう
それらのひとのどの人もまたどのひとも
五年のあいだにそれを大抵無くすのだ
生活のためにけずられたり
自分でそれをなくすのだ
すべての才や力や材というものは
ひとにとどまるものでない
ひとさえひとにとどまらぬ
云わなかったが、
おれは四月はもう学校に居ないのだ
恐らく暗くけわしいみちをあるくだろう
そのあとでおまえのいまのちからがにぶり
きれいな音の正しい調子とその明るさを失って
ふたたび回復できないならば
おれはおまえをもう見ない
なぜならおれは
すこしぐらいの仕事ができて
そいつに腰をかけてるような
そんな多数をいちばんいやにおもうのだ
もしもおまえが
よくきいてくれ
ひとりのやさしい娘をおもうようになるそのとき
おまえに無数の影と光の像があらわれる
おまえはそれを音にするのだ
みんなが町で暮したり
一日あそんでいるときに
おまえはひとりであの石原の草を刈る
そのさびしさでおまえは音をつくるのだ
多くの侮辱や窮乏の
それらを噛んで歌ふのだ
もしも楽器がなかったら
いいかおまえはおれの弟子なのだ
ちからのかぎり
そらいっぱいの
光でできたパイプオルガンを弾くがいい
引用:『春と修羅』
(筆者注:銀河鉄道にずぶ濡れの青年と二人の子供が乗り込んでくる。実は彼らはタイタニック号沈没による死者だった)
「あなた方はどちらからいらっしゃったのですか。どうなすったのですか。」さっきの燈台看守がやっと少しわかったように青年にたずねました。青年はかすかにわらいました。
「いえ、氷山にぶっつかって船が沈みましてね、わたしたちはこちらのお父さんが急な用で二ヶ月前一足さきに本国へお帰りになったのであとから発ったのです。私は大学へはいっていて、家庭教師にやとわれていたのです。ところがちょうど十二日目、今日か昨日のあたりです、船が氷山にぶっつかって一ぺんに傾きもう沈みかけました。月のあかりはどこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。ところがボートは左舷の方半分はもうだめになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちにも船は沈みますし、私は必死となって、どうか小さな人たちを乗せて下さいと叫びました。近くの人たちはすぐみちを開いてそして子供たちのために祈って呉れました。けれどもそこからボートまでのところにはまだまだ小さな子どもたちや親たちやなんか居て、とても押しのける勇気がなかったのです。それでもわたくしはどうしてもこの方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから前にいる子供らを押しのけようとしました。けれどもまたそんなにして助けてあげるよりはこのまま神のお前にみんなで行く方がほんとうにこの方たちの幸福だとも思いました。それからまたその神にそむく罪はわたくしひとりでしょってぜひとも助けてあげようと思いました。けれどもどうして見ているとそれができないのでした。子どもらばかりボートの中へはなしてやってお母さんが狂気のようにキスを送りお父さんがかなしいのをじっとこらえてまっすぐに立っているなどとてももう腸もちぎれるようでした。そのうち船はもうずんずん沈みますから、私はもうすっかり覚悟してこの人たち二人を抱いて、浮かべるだけは浮ぼうとかたまって船の沈むのを待っていました。誰が投げたかライフブイが一つ飛んで来ましたけれども滑ってずうっと向うへ行ってしまいました。私は一生けん命で甲板の格子になったとこをはなして、三人それにしっかりとりつきました。どこからともなく〔約二字分空白〕番の声があがりました。たちまちみんなはいろいろな国語で一ぺんにそれをうたいました。そのとき俄かに大きな音がして私たちは水に落ちもう渦に入ったと思いながらしっかりこの人たちをだいてそれからぼうっとしたと思ったらもうここへ来ていたのです。この方たちのお母さんは一昨年没くなられました。ええボートはきっと助かったにちがいありません、何せよほど熟練な水夫たちが漕いですばやく船からはなれていましたから。」そこらから小さないのりの声が聞えジョバンニもカムパネルラもいままで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して眼が熱くなりました。
(ああ、その大きな海はパシフィックというのではなかったろうか。その氷山の流れる北のはての海で、小さな船に乗って、風や凍りつく潮水や、烈しい寒さとたたかって、たれかが一生けんめいはたらいている。ぼくはそのひとにほんとうに気の毒でそしてすまないような気がする。ぼくはそのひとのさいわいのためにいったいどうしたらいいのだろう。)ジョバンニは首を垂れて、すっかりふさぎ込んでしまいました。
「なにがしあわせかわからないです。ほんとうにどんなつらいことでもそれがただしいみちを進む中でのできごとなら峠の上りも下りもみんなほんとうの幸福に近づく一あしずつですから。」
燈台守がなぐさめていました。
引用:『銀河鉄道の夜』
太宰治
「僕の作品なんかは、滅茶苦茶だけれど、しかし僕は、大望を抱いているんだ。その大望が重すぎて、よろめいているのが僕の現在のこの姿だ。君たちには、だらしのない無智な薄汚い姿に見えるだろうが、しかし僕は本当の気品といふものを知っている。松葉の形の干菓子を出したり、青磁の壺に水仙を投げ入れて見せたって、僕はちっともそれを上品だとは思わない。成金趣味だよ、失敬だよ。本当の気品というものは、真黒いどっしりした大きい岩に白菊一輪だ。土台に、むさい大きい岩が無くちゃ駄目なもんだ。それが本当の上品といふものだ。君たちなんか、まだ若いから、針金で支えられたカーネーションをコップに投げいれたみたいな女学生くさいリリシズムを、芸術の気品だなんて思っていやがる。」
引用:『津軽』
「悔恨の無い文学は、屁のかっぱです。悔恨、告白、反省、そんなものから、近代文学が、いや、近代精神が生れた筈なんですね。だから、――」
引用:『鷗』
私はいま、自分の創作年表とでも称すべき焼け残りの薄汚い手帳のペエジを繰りながら、さまざまの回想にふける。私がはじめて東京で作品を発表した昭和八年から、二十年まで、その十二箇年間、私はあのサロンの連中とはまるっきり違った歩調であるいて来た。
これではあの者たちと永遠に溶け合わないのも無理がない。あれは昭和二、三年の頃であったろうか。私がまだ弘前高等学校の文科生であって、しばしば東京の兄(この兄はからだの弱い彫刻家で、二十七歳で病死した)のところへ遊びに行ったが、この兄に連れられて喫茶店なるものにはいってみると、そこにはたいていキザに気取った色の白いやさ男がいて、兄は小声で、あれは新進作家の何の誰だ、と私に教え、私はなんてまあ浅墓な軽薄そうな男だろうと呆れ、つくづく芸術家という種族の人間を嫌悪した。
私は上品な芸術家に疑惑を抱いだき、「うつくしい」芸術家を否定した。田舎者の私には、どうもあんなものは、キザで仕様が無かったのである。
ベックリンという海の妖怪などを好んでかく画家の事は、どなたもご存じの事と思う。
あの人の画は、それこそ少し青くさくて、決していいものでないけれども、たしか「芸術家」と題する一枚の画があった。それは大海の孤島に緑の葉の繁ったふとい樹木が一本生はえていて、その樹の蔭にからだをかくして小さい笛を吹いているまことにどうも汚ならしいへんな生き物がいる。かれは自分の汚いからだをかくして笛を吹いている。孤島の波打際に、美しい人魚があつまり、うっとりとその笛の音に耳を傾けている。もし彼女が、ひとめその笛の音の主の姿を見たならば、きゃっと叫んで悶絶するに違いない。芸術家はそれゆえ、自分のからだをひた隠しに隠して、ただその笛の音だけを吹き送る。
ここに芸術家の悲惨な孤独の宿命もあるのだし、芸術の身を切られるような真の美しさ、気高さ、えい何と言ったらいいのか、つまり芸術さ、そいつが在るのだ。
私は断言する。真の芸術家は醜いものだ。喫茶店のあの気取った色男は、にせものだ。
アンデルセンの「あひるの子」という話を知っているだろう。小さな可愛かわいいあひるの雛の中に一匹、ひどくぶざまで醜い雛がまじっていて、皆の虐待と嘲笑ちょうしょうの的になる。意外にもそれは、スワンの雛であった。巨匠の青年時代は、例外なく醜い。それは決してサロン向きの可愛げのあるものでは無かった。
お上品なサロンは、人間の最も恐るべき堕落だ。しからば、どこの誰をまずまっさきに糾弾すべきか。自分である。私である。太宰治とか称する、この妙に気取った男である。
生活は秩序正しく、まっ白なシーツに眠るというのは、たいへん結構な事だが、(それは何としても否定できない魅力である!)しかし、自分ひとり大いに努力してその境地を獲得した途端に、急に人が変って様子ぶった男になり、かねてあんなに憎悪していたサロンにも出入し、いや出入どころか、自分からチャチなサロンを開設し半可通どもの先生になりはしないか。何せどうも、気が弱くてだらしない癖に、相当虚栄心も強くて、ひとにおだてられるとわくわくして何をやり出すかわかったもんじゃない男なのだから。
私はそのような成行きに対して、極度におびえていた。私がもしサロン的なお上品の家庭生活を獲得したならば、それは明らかに誰かを裏切った事になると考えていた。私は、いやらしいくらいに小心な債務家のようなものであった。
引用:『十五年間』
人間は一生、人間の愛憎の中で苦しまなければならぬものです。のがれ出る事は出来ません。忍んで、努力を積むだけです。学問も結構ですが、やたらに脱俗を衒(てら)うのは卑怯です。もっと、むきになって、この俗世間を愛惜し、愁殺し、一生そこに没頭してみて下さい。神は、そのような人間の姿を一ばん愛しています。
引用:『竹青』
(筆者注:役者になった主人公が兄と再会する場面)
二箇月振りで帰ると、東京は既に師走である。僕も変った。兄さんが、東京駅へ迎えに来てくれていた。僕は、兄さんの顔を見て、ただ、どぎまぎした。兄さんは、おだやかに笑っている。
僕は、兄さんと、もうはっきり違った世界に住んでいる事を自覚した。僕は日焼けした生活人だ。ロマンチシズムは、もう無いのだ。筋張った、意地悪のリアリストだ。変ったなあ。
黒いソフトをかぶって、背広を着た少年。おしろいの匂いのする鞄をかかえて、東京駅前の広場を歩いている。これがあの、十六歳の春から苦しみに苦しみ抜いた揚句の果に、ぽとりと一粒結晶して落ちた真珠の姿か。あの永い苦悩の、総決算がこの小さい、寒そうな姿一つだ。すれちがう人、ひとりとして僕の二箇年の、滅茶苦茶の努力には気がつくまい。よくも死にもせず、発狂もせずに、ねばって来たものだと僕は思っているのだが、よその人は、ただ、あの道楽息子も、とうとう役者に成りさがった、と眉をひそめて言うだろう。芸術家の運命は、いつでも、そんなものだ。
誰か僕の墓碑に、次のような一句をきざんでくれる人はないか。
「かれは、人を喜ばせるのが、何よりも好きであった!」
僕の、生れた時からの宿命である。俳優という職業を選んだのも、全く、それ一つのためであった。ああ、日本一、いや、世界一の名優になりたい! そうして皆を、ことにも貧しい人たちを、しびれる程に喜ばせてあげたい。
引用:『正義と微笑』
私は、この世の中に生きている。しかし、それは、私のほんの一部分でしか無いのだ。同様に、君も、またあのひとも、その大部分を、他のひとには全然わからぬところで生きているに違いないのだ。
私だけの場合を、例にとって言うならば、私は、この社会と、全く切りはなされた別の世界で生きている数時間を持っている。それは、私の眠っている間の数時間である。私はこの地球の、どこにも絶対に無い美しい風景を、たしかにこの眼で見て、しかもなお忘れずに記憶している。
私は私のこの肉体を以って、その風景の中に遊んだ。記憶は、それは、現実であろうと、また眠りのうちの夢であろうと、その鮮やかさに変りが無いならば、私にとって、同じような現実ではなかろうか。
私は、睡眠のあいだの夢に於いて、或る友人の、最も美しい言葉を聞いた。また、それに応ずる私の言葉も、最も自然の流露の感じのものであった。
また私は、眠りの中の夢に於いて、こがれる女人から、実は、というそのひとの本心を聞いた。そうして私は、眠りから覚めても、やはり、それを私の現実として信じているのである。
夢想家。
そのような、私のような人間は、夢想家と呼ばれ、あまいだらしない種族のものとして多くの人の嘲笑と軽蔑の的にされるようであるが、その笑っているひとに、しかし、笑っているそのお前も、私にとっては夢と同じさ、と言ったら、そのひとは、どんな顔をするであろうか。
私は、一日八時間ずつ眠って夢の中で成長し、老いて来たのだ。つまり私は、所謂この世の現実で無い、別の世界の現実の中でも育って来た男なのである。
私にはこの世の中の、どこにもいない親友がいる。しかもその親友は生きている。また私には、この世のどこにもいない妻がいる。しかもその妻は、言葉も肉体も持って、生きている。
(中略)
いつも夢の中で現れる妻が、「あなたは、正義ということをご存じ?」
と、からかうような口調では無く、私を信頼し切っているような口調で尋ねた。
私は、答えなかった。
「あなたは、男らしさというものをご存じ?」
私は、答えなかった。
「あなたは、清潔ということをご存じ?」
私は、答えなかった。
「あなたは、愛ということをご存じ?」
私は、答えなかった。
やはり、あの湖のほとりの草原に寝ころんでいたのであるが、私は寝ころびながら涙を流した。
すると、鳥が一羽飛んで来た。その鳥は、蝙蝠に似ていたが、片方の翼の長さだけでも三米(メートル)ちかく、そうして、その翼をすこしも動かさず、グライダのように音も無く私たちの上、二米くらい上を、すれすれに飛んで行って、そのとき、鴉の鳴くような声でこう言った。
「ここでは泣いてもよろしいが、あの世界では、そんなことで泣くなよ。」
引用:『フォスフォレッセンス』
家庭の幸福は諸悪の本(もと)
引用:『家庭の幸福』
坂口安吾
(筆者注:安吾が太宰治の死を受けて書いた追悼文)
死ぬ時は、ただ無に帰するのみであるという、このツツマシイ人間のまことの義務に忠実でなければならぬ。私は、これを、人間の義務とみるのである。生きているだけが、人間で、あとは、ただ白骨、否、無である。そして、ただ、生きることのみを知ることによって、正義、真実が、生れる。生と死を論ずる宗教だの哲学などに、正義も、真理もありはせぬ。あれは、オモチャだ。
然し、生きていると、疲れるね。かく言う私も、時に、無に帰そうと思う時が、あるですよ。戦いぬく、言うは易く、疲れるね。然し、度胸は、きめている。是が非でも、生きる時間を、生きぬくよ。そして、戦うよ。決して、負けぬ。負けぬとは、戦う、ということです。それ以外に、勝負など、ありやせぬ。戦っていれば、負けないのです。決して、勝てないのです。人間は、決して、勝ちません。ただ、負けないのだ。
勝とうなんて、思っちゃ、いけない。勝てる筈が、ないじゃないか。誰に、何者に、勝つつもりなんだ。
引用:『不良少年とキリスト』
それならば、生存の孤独とか、我々のふるさとというものは、このようにむごたらしく、救いのないものでありましょうか。私は、いかにも、そのように、むごたらしく、救いのないものだと思います。(中略)私は文学のふるさと、或いは人間のふるさとを、ここに見ます。文学はここから始まる――私は、そうも思います。
アモラルな、この突き放した物語だけが文学だというのではありません。否、私はむしろ、このような物語を、それほど高く評価しません。なぜなら、ふるさとは我々のゆりかごではあるけれども、大人の仕事は、決してふるさとへ帰ることではないから。……だが、このふるさとの意識・自覚のないところに文学があろうとは思われない。文学のモラルも、その社会性も、このふるさとの上に生育したものでなければ、私は決して信用しない。そして、文学の批評も。私はそのように信じています。
引用:『文学のふるさと』
宮崎駿
――― 「この世は生きるに値すると子供に伝えたい」という自身の言葉について。
宮崎 自分の好きな英国の児童文学作家でロバート・ウェストールという人がいるが、彼のいくつかの作品の中に、自分の考えなくてはいけないことが充満している。その中にこういうようなセリフがある。「この世はひどいものである。君はこの世に生きていくには気立てがよすぎる」。少しもほめ言葉ではない。それでは生きていけないぞと言っている言葉。本当に胸を打たれた。
(「この世は生きるに値する」という言葉は)僕が発信しているのではなく、僕はいろんなものを多くの読み物や昔見た映画などからいっぱい受け取っているのだと思う。(それらを作った人々は)繰り返し「この世は生きるに値する」と言い伝え、ほんとかなと思いつつ死んでいったのではないか。僕もそれを受け継いでいるのだと思っている。
ヴィクトール・フランクル
(筆者注:ナチス強制収容所から強制労働の作業現場に向かう道中、過酷な雪道に耐えながら著者は今ここにいない妻に思いをはせる)
わたしはときおり空を仰いだ。星の輝きが薄れ、分厚い黒雲の向こうに朝焼けが始まっていた。今この瞬間、わたしの心はある人の面影に占められていた。精神がこれほどいきいきと面影を想像するとは、以前のごくまっとうな生活では思いもよらなかった。わたしは妻と語っているような気がした。妻が答えるのが聞こえ、微笑むのが見えた。まなざしでうながし、励ますのが見えた。妻がここにいようがいまいが、その微笑みは、たった今昇ってきた太陽よりも明るくわたしを照らした。
そのとき、ある思いがわたしを貫いた。何人もの思想家がその生涯の果てにたどり着いた真実、何人もの詩人がうたいあげた真実が、生まれてはじめて骨身にしみたのだ。愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ、という真実。今わたしは、人間が詩や思想や信仰をつうじて表明すべきこととしてきた、究極にして最高のことの意味を会得した。愛により、愛のなかへと救われること! 人は、この世にもはやなにも残されていなくても、心の奥底で愛する人の面影に思いをこらせば、ほんのいっときにせよ至福の境地になれるということを、わたしは理解したのだ。
収容所に入れられ、何かをして自己実現する道を断たれるという、思いつくかぎりでもっとも悲惨な状況、できるのはただこの耐えがたい苦痛に耐えることしかない状況にあっても、人は内に秘めた愛する人のまなざしや愛する人の面影を精神力で呼び出すことにより、満たされることができるのだ。
引用:『夜と霧 新版』

